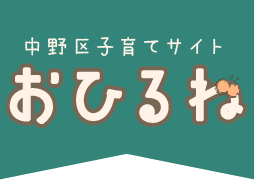教育・保育給付支給認定証の申請
ページID:193294769
更新日:2024年8月20日
認可保育所、認定こども園(保育園的利用)、地域型保育事業(認可家庭的保育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業、認可居宅訪問型保育事業)等で保育を受けたい方は、保育の必要性に応じた「認定(2号または3号認定)」の申請が必要です。
その後、区から『教育・保育給付支給認定証』が交付されます。認定を受けていない方は、保育所等の入園申し込みと同時に申請することができます。
目次
就学前のお子さんを持つ保護者から申請を受け、認定区分や保育を必要とする事由、保育の必要量を認定することです。保育所等を利用する場合、その認定を元に保育にかかる費用を区が保護者に給付します。給付費用は確実に教育・保育の費用に充てるため、区から直接保育所等へ支払います。(法定代理受領)
なお、保育所等の入園は、保育所等利用調整基準により決定しますので、教育・保育給付支給認定によって入園に有利・不利は生じません。入園に関する詳細はこちらのページから確認ください。
| 認定区分 | お子さんの年齢と教育・保育の希望 |
|---|---|
| 2号認定 | 満3歳以上で保育(保育園・認定こども園・地域型保育事業)を希望する場合 |
| 3号認定 | 満3歳未満で保育(保育園・認定こども園・地域型保育事業)を希望する場合 |
認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の事由に該当する場合です。
認定する事由・認定期間は、保護者の該当する事由のうち、認定期間の短い方を適用します。
| 保育の必要性の事由 | 認定期間 |
|---|---|
| 就労(月48時間以上)を常態としている場合 | 就労している期間 |
| 疾病や障がいがあり保育に支障がある場合 | 必要な期間 |
| 親族の方を日中常時介護・看護(週3日以上かつ日中4時間以上)している場合 | |
| 災害の復旧にあたっている場合 | |
| 社会的養護が必要な場合 | |
| 出産の前後の場合 | 出産予定月及びその前後2ヶ月 (多胎妊娠の場合は14週間前から) |
| 求職活動中や就労内定中の場合 | 90日 入園希望日から起算して90日目が属する月の月末 |
| 就学(学校教育法に定める学校、職業訓練校等)で月48時間以上の受講を常態している場合 | 必要な期間 |
| 上記以外で特に保育が必要と認められる場合 | 必要な期間 |
※認定期間中に満3歳になった場合は、3号認定から2号認定へ変更します(手続き不要)。
※認定期間中に保育の必要性の事由がなくなった場合、認定は失効します。
| 区分 | 保育時間 |
|---|---|
| 保育標準時間 | 最長11時間 |
| 保育短時間 | 最長8時間 |
※就労、介護・看護、就学は、保育が必要となる時間に応じ、保育標準時間または保育短時間となります。
※妊娠・出産、疾病・障がい、災害、求職活動、社会的養護または育児休業期間中は保育標準時間としますが、保護者が希望する場合は保育短時間とします。
※実際の保育時間は、就労・介護・看護・就学・求職活動等の状況に応じて保育園と相談して決定します。
 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)
教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)- 父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類
 個人番号(マイナンバー)の提供について(PDF形式:116KB)
個人番号(マイナンバー)の提供について(PDF形式:116KB)- 身元確認書類のコピー
- マイナンバー確認書類のコピー
| 就労 | 会社員・パート・派遣社員等の方 | |
|---|---|---|
経営主・自営業・経営主が親族の方 |
※上記2の書類がご提出いただけない場合は下記2点をご提出ください。 | |
| 疾病 | ||
| 障がい | 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー | |
親族の介護・看護 |
| |
| 妊娠・出産 | 母子健康手帳出産予定日が記載されているページのコピー | |
| 災害復旧 | り災・被災証明書のコピー | |
| 求職活動 | 求職活動を証明する書類( | |
不存在(ひとり親の方) | 死別、離婚、未婚の方 | 次のいずれかのコピー
|
| 上記以外の方 | ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの | |
| 【顔写真付証明書】 | マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、在留カード(両面) 等 |
|---|---|
| 【顔写真なし証明書】 | 健康保険証(両面)、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証 等 |
| 右記の書類から1点 | マイナンバーカード(マイナンバー記載面)、マイナンバーが記載された住民票の写し等 |
|---|
支給認定証は、原則、申請のあった日から30日以内に交付します。認定内容に変更がない限り、大切に保管してください。
なお、認定証の申請方法は以下のとおりです。認定の希望開始期間よりも前に必ず申請してください。
入園・転園の申し込みと同時に教育・保育支給認定の申請ができます。入園・転園の詳細はこちらのページをご確認ください。
こちらのページからご確認ください。
こちらのページからご確認ください。
![]() 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)を記入し窓口や郵送で届出いただくか、
教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)を記入し窓口や郵送で届出いただくか、![]() 電子申請(外部サイト)から申請してください。
電子申請(外部サイト)から申請してください。
支給認定証を再交付するためには、![]() 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)を記入し窓口や郵送で届出いただくか、
教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)を記入し窓口や郵送で届出いただくか、![]() 電子申請(外部サイト)から申請してください。
電子申請(外部サイト)から申請してください。
※窓口・郵送での届出の場合は ![]() 記入例(PDF形式:150KB)を参考にご記入ください。再交付時は記入不要の箇所があります。
記入例(PDF形式:150KB)を参考にご記入ください。再交付時は記入不要の箇所があります。
※再交付には1週間程お時間をいただいております。
認定区分や事由、保育の必要量などの認定内容を変更する場合は申請が必要です。
- 窓口や郵送で届出を希望の場合は
 教育・保育給付支給認定申請書(PDF形式:99KB)、
教育・保育給付支給認定申請書(PDF形式:99KB)、 教育・保育給付支給認定申請内容変更届書(PDF形式:84KB)と申請内容に応じた必要書類をご提出ください。
教育・保育給付支給認定申請内容変更届書(PDF形式:84KB)と申請内容に応じた必要書類をご提出ください。 - 電子での提出
・ 在園中(転園申請中の方は除く)の方(外部サイト)
在園中(転園申請中の方は除く)の方(外部サイト)
・ 入園・転園申請中の方(外部サイト)
入園・転園申請中の方(外部サイト)
必要書類は申請フォーム内で添付できます。
※家庭状況・支給認定内容に変更があった場合の必要書類をご確認ください。
※認定は居住区の自治体が交付するため、区外へ転出された場合は転出先で改めて認定の申請が必要です。
関連情報
お問合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。