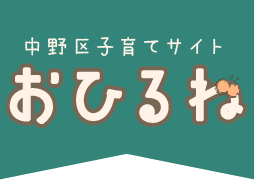児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス
ページID:735177357
更新日:2025年11月28日
児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの種類
1.児童発達支援(対象児:未就学児)
2.放課後等デイサービス(対象児:就学児)
3.居宅訪問型児童発達支援
4.保育所等訪問支援
事業所一覧はこちらからご確認ください。
未就学で支援が必要なお子さんを対象として、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応支援等を行います。個々の状況及び発達過程・特性等に応じた発達上の課題を達成させていくための本人への発達支援・家庭への支援・幼稚園・保育園等と連携を図りながら支援を行います。
就学している支援が必要なお子さんを対象として、 授業終了後又は学校休業日に、生活能力向上のための支援、社会との交流促進等を行います。学校や家庭とは異なる時間・空間・人・体験を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行います。
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の支援、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な支援を行います。
保護者の依頼に基づいて、対象児が通っている保育園・幼稚園・認定こども園等を支援員が訪問し、保育園や幼稚園と連携して集団生活上のお子さんの成長、発達を支援していきます。対象児は中野区にお住まいで、保育園、幼稚園等に通園するお子さんです。
詳しくは下記をご覧ください。
・![]() 保育所等訪問支援について(PDF形式:332KB)
保育所等訪問支援について(PDF形式:332KB)
サービス利用の流れ
障害児通所支援事業のサービスを利用する場合は、お住まいの地域を担当するすこやか福祉センターへご相談ください。保護者の方からお子さんの心配な点等を伺ったうえで、適切な支援方法を一緒に考えます。
![]() 受給者証についてはこちらをご確認ください。(PDF形式:152KB)
受給者証についてはこちらをご確認ください。(PDF形式:152KB)
未就学のお子さんは、すこやか福祉センター相談後、区立療育センターで療育相談を受けます。療育相談の結果をふまえて福祉サービス利用の必要性を判断します。但し、以下の書類等をお持ちの方は、その必要はありません。
(1)障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(2)特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
(3)その他支援が必要であることがわかる診断書、意見書、発達検査結果等の書類
小学校入学以降のお子さんはまず、すこやか福祉センターにご相談ください。支援が必要であることがわかる医師の意見書、発達検査結果等の書類を持参するか、あるいは区立療育センターゆめなりあの療育相談をうけていただく場合があります。![]() 療育相談事前アンケート(ワード形式)(ワード:29KB)
療育相談事前アンケート(ワード形式)(ワード:29KB)![]() 療育相談事前アンケート(PDF形式)(PDF形式:125KB)
療育相談事前アンケート(PDF形式)(PDF形式:125KB)
受給者証取得について詳しくは下記をご覧ください。
(参考:![]() すこやか福祉センターへの利用相談から始まる中野区の発達支援全体図(PDF形式:467KB))
すこやか福祉センターへの利用相談から始まる中野区の発達支援全体図(PDF形式:467KB))
【相談窓口】
中部すこやか福祉センター電話番号 03-3367-7788
北部すこやか福祉センター電話番号 03-3388-0240
南部すこやか福祉センター電話番号 03-3380-5551
鷺宮すこやか福祉センター電話番号 03-3336-7111
療育相談で福祉サービスの必要性があると結果がでた又は、診断書、意見書、発達検査結果等の書類をお持ちの方は、障害児通所支援の利用申請をしてください。(受給者証取得)
各すこやか福祉センターに併設されるすこやか障害者相談支援事業所で申請を受け付けます。
担当区域は「私のまちのすこやか福祉センター」をご覧ください。
【申請受付窓口】
中部すこやか障害者相談支援事業所電話番号 03-3367-7810
北部すこやか障害者相談支援事業所電話番号 03-5942-5800
南部すこやか障害者相談支援事業所電話番号 03-5340-7888
鷺宮すこやか障害者相談支援事業所電話番号 03-6265-5770
利用申請後、区から申請者へ障害児支援利用計画案の作成を依頼しますので、提出をお願いします。 基本的には指定障害児相談支援事業者と契約をし、指定障害児相談支援事業者が作成します。作成には費用はかかりません。
(参考:![]() 「障害児支援利用計画案」等作成の流れ(PDF形式:244KB))
「障害児支援利用計画案」等作成の流れ(PDF形式:244KB))
(参考:![]() (指定障害児相談支援事業所一覧)(PDF形式:309KB)
(指定障害児相談支援事業所一覧)(PDF形式:309KB)
調査員(すこやか障害者相談支援事業所担当者)がお子さんの状況やサービス利用について国の基準に基づいて調査を行います。
上記4の調査及び障害児支援利用計画案を勘案し、支給決定を行います。
支給決定後、区から通所受給者証を送付します。
通所受給者証を提示し、利用する事業者と契約をします。
サービスの利用を開始します。
利用者負担について
1.未就学の方
(1)児童発達支援等の利用者負担の無償化
令和元年10月1日より、就学前の子どもを支援するため児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。 無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。食費等の実費で負担しているものは引き続きお支払いいただきます。詳しくは、関連情報「 幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
(2)0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の無償化(区独自)
国制度により3~5歳の児童の利用者負担は無償化されていますが、令和7年9月分より児童発達支援事業等を利用する0歳から2歳までの利用者負担についても、中野区独自の助成制度(※)で無償化します。これにより対象サービスを利用する就学前の全ての児童の利用者負担額が無償化されることになりました。
※満3歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象
新たに中野区のサービスを受けるときは、申請が必要です。詳しくは、関連情報「![]() 0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の第1子無償化を実施します。」をご覧ください。
0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の第1子無償化を実施します。」をご覧ください。
2.就学されている方
児童の保護者の所得に応じて、ひと月に負担する上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。
| 所得区分 | 所得の状況(住民票上の世帯) | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 区市町村民税所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 区市町村民税所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
利用者負担上限月額の管理
複数の事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に利用者負担上限月額の管理を依頼します。
高額障害児通所給付費等の支給(高額償還)について
同一の月に同一人が障害児通所支援、障害福祉サービス、補装具費の支給などを利用したり、同一世帯の複数の人が同一の月に障害児通所支援、障害福祉サービス、補装具費の支給などを利用した際に、一か月の自己負担額の合計が世帯の基準額を超えた時に、超えた分の額が助成されます。対象者には区から通知を送付します。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。