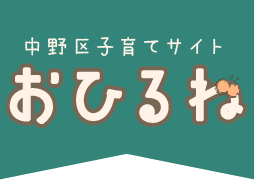認可保育所等の保育料
ページID:433381419
更新日:2025年9月5日
【重要】2025年9月分以降の保育料について(保育料第1子無償化の実施)
2025年9月から保育料第1子無償化を実施し、認可保育所・地域型保育事業を利用する0~2歳児クラス(課税世帯)第1子の保育料について、所得階層に関わらず無料といたします。これをもって、中野区にお住まいのすべてのお子さまの基本保育料が無料になります。なお、以下の費用については、無償化の対象とはなりませんのでご注意ください。
※無償化の処理は区で行うため、保護者の手続きは不要です。
※本負担軽減は、東京都の保育所等利用世帯負担軽減事業により実施しております。今後、東京都の保育所等利用世帯負担軽減事業が改廃された場合は、本負担軽減の取扱いが変更となる場合があります。
延長保育料
延長保育は2025年9月以降も無償化の対象外です。詳細はこちらのページをご確認ください。
2025年8月分までの保育料について
これより下の項目は2025年8月分までの保育料に関する記載です。
以下のお子さまにおいては2025年8月以前から保育料は無償化済みですが、0~2歳児クラス(課税世帯)の第1子につきましては保育料が発生します。保育園運営に必要な経費の一部分に充てているため、納期限を守ってお支払いください。
【2025年8月以前から無償化のお子さま】
- 3~5歳児クラス
- 0~2歳児クラス(住民税非課税世帯)
- 0~2歳児クラス(住民税課税世帯)の第2子以降
保育料表
保育料は、認可保育所・認定こども園(保育園的利用)・地域型保育事業で共通です。また、保育の必要量に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分の保育料が設定されています。詳細は![]() 保育料表(令和5年10月~令和7年8月)(PDF形式:178KB)をご覧ください。
保育料表(令和5年10月~令和7年8月)(PDF形式:178KB)をご覧ください。
保育料に関する注意事項
- 保育料を決定する年齢は、入園年度の4月1日現在の満年齢(クラス年齢)です。
年度途中で誕生日を迎えられても保育料は変わりません。 - 保育料は月額のため毎月1日現在に在籍している場合は、当月分の保育料をお支払いいただきます。
通園日数が少ない場合(1日も通園がない場合を含みます。)でも、保育料の日割り計算は行いません。 - 個別にお弁当を持参いただいた場合であっても、保育料の免除や減額は行いません。
- 保育料の支払い期限は毎月月末(月末が休業日の場合は、翌営業日)です。
※口座振替払いの引落日も同様です。 - 保育料を期限までにお支払いただけない場合は、書面による督促・催告のほか、滞納処分(差し押さえ)を行う場合があります。
- 保育料は、認可保育所に在園している場合は中野区へお支払いください。
また、認定こども園、地域型保育事業(認可家庭的保育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業、認可居宅訪問型保育事業)に在園している場合は各施設(事業者)へお支払いください。
算定方法および算定時期
算定根拠となる年度における世帯の住民税所得割合算額を基に、保育料を決定します。
保育料の決定は毎年4月と9月の年2回行います。
| 決定月 | 対象期間 | 算定根拠となる住民税所得割額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 2025年4月~2025年8月 | 2024年度分(2023年分所得) | 保育料はクラス年齢より決定します。 | ||||||||
| 2025年9月 | 2025年9月~2026年3月 | 2025年度分(2024年分所得) | |||||||||
- 算定は、住宅借入金特別控除や寄付金控除等の税額控除前の所得割額で行います。
詳しくは、 区民税所得割額の確認方法について(PDF形式:325KB)をご覧ください。
区民税所得割額の確認方法について(PDF形式:325KB)をご覧ください。 - 海外に居住しており日本国内で住民税が課税されていない場合は、前年の収入状況等から推計した住民税額で算定します。
- お子さんが生計を一にする同居の祖父母に扶養されている場合、扶養している祖父母の住民税所得割額も保育料の算定根拠とする場合があります。
- 結婚や離婚等により保護者に変更があった場合等は、保育料を再算定し、変更します。保育料の変更は、原則変更手続きを行った月の翌月分からとなります。
- 生活保護受給世帯、住民税非課税世帯および里親制度を利用している世帯の場合、保育料はかかりません。
住民税未申告等による保育料の最高額決定について
次の事由等で住民税未決定の方は、保育料を最高階層(最高額)で決定します。
なお、住民税が決定された場合または収入のわかる書類を提出した場合、当年度の保育料に限り、保育料を再算定します。
- 保護者が住民税の申告をしていない。
※育休中で所得がない場合でも、個別に住民税の申告が必要となります。 - 4月から8月分保育料の場合は前年1月1日時点、9月から3月分保育料の場合は当年1月1日時点で中野区外に居住し、前住地の課税証明が提出されていない。
※ただし、前住所地で住民税が決定され、かつ、入園申込時に個人番号(マイナンバー)関係書類を提出している方は除きます。 - 4月から8月分保育料の場合は前年1月1日時点、9月から3月分保育料の場合は当年1月1日時点で海外に居住し、収入のわかる書類(給与明細・勤務先が発行する収入証明書など)が提出されていない。
※上記収入のわかる書類の提出にあたっては、4月から8月分保育料の場合は前々年1月から12月の収入、9月から3月分保育料の場合は前年1月から12月の収入を証する必要があります。
修正申告などにより住民税所得割額に変更があった方へ
修正申告等により住民税所得割額に変更があった場合、当年度の保育料に限り、再算定します。
保育料の再算定を行った結果、既にお支払いいただいた保育料に不足額が生じた場合は不足額の請求を、過払いが生じた場合は未払いの保育料への充当または還付を行います。
多子世帯に対する保育料負担軽減
保護者と生計を一にするお子さんが2人以上いる場合は、年齢の高い順から数えて2番目以降のお子さんの保育料は 無料となります。
生計を一にするお子さんには、就学や療養等のため別居しており、生活費や学資金、療養費等を支払っているお子さんを含みます。
また、本負担軽減を適用するにあたり、保護者の所得や生計を一にするお子さんの保育園等の在籍の有無による制限はありません。
提出書類
別居している生計を一にするお子さんがいる場合は、次に挙げる書類の提出が必要となります。
 多子世帯の保育料負担軽減に係る申告書(PDF形式:111KB)
多子世帯の保育料負担軽減に係る申告書(PDF形式:111KB)- 別居しているお子さん自身の住民票の写し
- 生計を一にしていることがわかる書類 (生活費・学資金等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等)
- 別居の理由がわかる書類(在学証明書、診断書等)
要保護世帯(ひとり親世帯・同一世帯に障がい者のいる世帯)に対する負担軽減
ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の住民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)は、保護者と生計を一にするお子さんを対象に年齢の高い順に数えて、1番目のお子さんの保育料は半額、2番目以降のお子さんの保育料は無料となります。
提出書類
次の1・2のいずれかに該当する場合は、次に挙げる書類の提出が必要となります。
- 別居している生計を一にするお子さんがいる
・ 多子世帯の保育料負担軽減に係る申告書(PDF形式:111KB)
多子世帯の保育料負担軽減に係る申告書(PDF形式:111KB)
・別居しているお子さん自身の住民票の写し
・生計を一にしていることがわかる書類 (生活費・学資金等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等)
・別居の理由がわかる書類(在学証明書、診断書等) - 障がい者がいる
・障がいの種別・等級が確認できる障害者手帳の写し
※障害者手帳の写しを提出されていない場合に限ります。
保育料の減額について
保育料が減額になる場合があります。
下表の減額の事由に該当する場合は![]() 保育料減額申請書(PDF形式:42KB)と必要書類を揃えて下記担当へ提出してください。
保育料減額申請書(PDF形式:42KB)と必要書類を揃えて下記担当へ提出してください。
| 減額の事由 | 保育料減額申請書 以外の必要書類 |
|---|---|
| 生活保護を受けたとき | 生活保護受給証明書 |
| 災害などで損害を受けたとき | り災証明書、保険金の支払証明書 |
| 生計を一にしている世帯に、身体障害者手帳1・2級、 愛の手帳1~3度または精神障害者保険福祉手帳1~3級 の交付を受けた者がいる場合 | 手帳の写し |
上記の事由以外にも保育料が減額になる場合があります。詳しくはご相談ください。
保育料支払証明書の発行について
保育料の支払方法を口座振替としている場合、領収書は発行されません。
領収書の代替としまして、申請に基づき、中野区が保育料支払証明書を発行します。
保育料支払証明書が必要な場合は、下記リンク先より電子申請を行ってください。![]() 保育料支払証明書発行依頼書の電子申請へ(パソコン・スマートフォン)(外部サイト)
保育料支払証明書発行依頼書の電子申請へ(パソコン・スマートフォン)(外部サイト)
注意事項
- 保育料支払証明書は、証明を希望する期間の最終月の翌月15日以降に発行可能となります。
- 保育料支払証明書の発行対象となる保育所は、認可保育所のみです。
また、支払証明の対象となる保育料は、区立認可保育所の場合は基本保育料及び延長保育料(日額利用を含む)、私立認可保育所の場合は基本保育料のみです。
延長保育料
延長保育の詳細はこちらのページをご確認ください。
関連ファイル
 保育料表(令和5年10月~令和7年8月)(PDF形式:178KB)
保育料表(令和5年10月~令和7年8月)(PDF形式:178KB) 中野区認可保育園保育料口座振替対応金融機関一覧(PDF形式:69KB)
中野区認可保育園保育料口座振替対応金融機関一覧(PDF形式:69KB) 多子世帯の保育料負担軽減に係る申告書(PDF形式:111KB)
多子世帯の保育料負担軽減に係る申告書(PDF形式:111KB) 区民税所得割額の確認方法について(PDF形式:325KB)
区民税所得割額の確認方法について(PDF形式:325KB)
関連情報
お問合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
電話番号 03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。